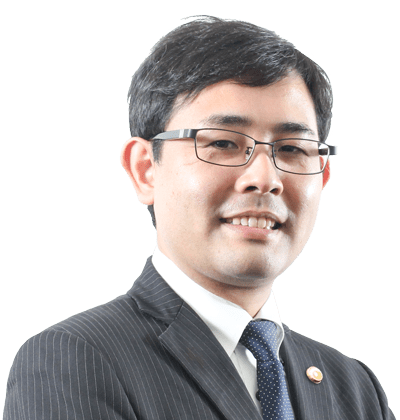10月11日土曜日から、川越の某映画館にて、とある映画が上映されます。
「揺さぶられっ子症候群(Shaken Baby Syndrome)」事件といわれる複数の事件で起きた冤罪事
・・・(続きはこちら)10月11日土曜日から、川越の某映画館にて、とある映画が上映されます。
「揺さぶられっ子症候群(Shaken Baby Syndrome)」事件といわれる複数の事件で起きた冤罪事件をテーマにした映画です。
実際に、相当数の逮捕・勾留がなされ、多数の事件で起訴もされました。
しかしながら、科学的な観点から様々な検討が行われ、結果として無罪判決が続出したという事件です。
弁護士法第1条第1項は「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」としています。
つまり、弁護士は、基本的人権を擁護することを第一義的な至上命題としてもっておかなければならないということです
(弁護士が依頼者の権利を守るというのは当然の話で、だから何でも許されるというものではないということも当然の話ですが。)。
さて、冤罪というのは、無実の人が犯罪者として扱われ、身体拘束や処罰を受けることで、関係するすべての人の人生を狂わせてしまうものです。
犯人と疑われた人の人生を破壊するだけでなく、その周りの人たちも、人生が破壊されてしまいます。
被害者にとっても、真犯人が取り逃がされてしまったという事実が突き付けられてしまうのです。
つまり、冤罪事件は、憲法13条第1文が認めている基本的人権である個人の尊厳を、徹底的に破壊してしまうものなのです。
そのため、弁護士は、冤罪をなくすために日々争っていますし、当然、裁判官も検察官も警察官も、冤罪を生じさせないように刑事司法を動かしています。
しかし、弁護士も裁判官も検察官も警察官も、人です。
人は間違いを犯します。
そのとき、何を思い、何を考えるか、それこそが、次の冤罪被害を生じさせないために最も大事なことであるはずです。
そうだとしても、冤罪事件は次々に起きてしまいます。
それがなぜなのか、このブログを読んでいただいている方にとっても、考える一つのきっかけになる映画かもしれません。
埼玉弁護士会でも、2月に冤罪事件を考えるシンポジウムを予定しています。
このシンポジウムの詳細については、改めてブログにも書きたいと思います。